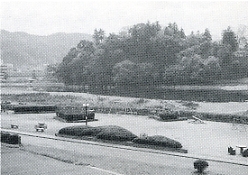データベース『えひめの記憶』
河川流域の生活文化(平成6年度)
(2)肱川の流れの中で
**さん(大洲市中村 大正2年生まれ 81歳)
**さん(大洲市中村 大正5年生まれ 78歳)
**さん(大洲市中村 昭和4年生まれ 65歳)
**さん(大洲市五郎 昭和15年生まれ 54歳)
ア 筏(いかだ)や川舟が遊び場だったころ
昔は、肱川は川幅が広く、水量も豊かで、水も澄んでおり、予供たちの格好の遊び場であった。子供たちにとって、肱川との付き合いが始まるのは、4、5歳ころからで、夏は、一日中、川で遊んでいた。遊びの中心はやはり泳ぎであった。当時は、裸の子供がほとんどであったが、男の子の中には、黒いサッポーターをしている子もいた。また、中学生になると、赤いフンドシであった。
子供たちが、よく泳いだのは、城山の下であった。そこには、烏帽子岩(えぼしいわ)とよばれる岩があり、中学生などは、そこでよく飛び込みをやっていた。ただ、そこは、たいへん深い淵になっており、渦が巻いて危険であったので、「気を付けんと、エンコ(カッパ)に引き込まれる。」などと、よく言われた。その下流には、もう一つ「権(ごん)べ淵」とよばれる淵があり、ここでもよく飛び込みが行われた。岩の上から飛び込むこともあったが、淵の上に伸びた木の枝から飛び込むことも多かった。男の子は頭から飛び込むが、女の子は足から飛び込むので、鼻に水が入らないように木の葉をくわえて鼻をふさいで飛び込んだりしていた。
子供たちは、中村から対岸のお城の下まで、よく肱川を泳いで渡った。そこにはちょうど渡し船があったので、慣れないうちは船のへりにつかまりながら泳ぎ、それを繰り返すうちに、自然に泳ぎを覚えて、一人で渡れるようになった。当時は、みんなが泳いで渡るので、自分も泳がなければならないような気になっていた。肱川を往来する筏や川舟も子供たちの遊び場となった。筏にくっついて肱川を下ったり、潜って筏の下をくぐり抜けたりして、筏の船頭さんにしかられることもあったが、そういう子供たちを乗せてくれる船頭さんもいて、筏から飛び込むのも、一つの楽しみであった。
肱川は、子供たちにとって最高の遊び場であったが、一方では、水量も多く、流れが複雑で、たいへん危ない川でもあり、水難事故も少なくなかった。**さんのお父さんは、泳ぎが上手であったので、溺れかけた子供をよく助けたそうで、冗談まじりに、「表彰してもらわんといかん。」とよく話されていたという。子供たちの間でも、年長者から、「ここへは、行ったらいかん。」とか、「お盆には、川に入ったらいかん。」と教えられた。危険防止については、年長者がリーダーとして、よく気を配っていたのである。
イ 魚取りのこと
泳ぎとともに、特に男の子の遊びの中心になったのが、魚取りである。
魚を取る方法としてよく用いられたのが、ビンヅケであった。これは、ガラス瓶の中に味噌(みそ)を入れて川にしばらく沈めておき、中に入ってきたハヤやモロコなどの小魚を取るものである。**さんは、ビンヅケに使う味噌をもらいに、「おっちゃん、腐り味噌おくれや。」と近所の味噌屋さんに行っては、「オラとこは、腐り味噌など売っとらせん。」と、よくしかられたそうである。朝から晩まで1日中川につかって、たくさんの魚を取り、焼いたり煮たりして家の食卓を飾った。
女の子や小さな子供は、日本手拭(てぬぐい)で小さな魚をすくって遊んだ。年長者が深い方に入り、小さい子が岡の方にいて、二人で手拭の両端をもって小魚(子供たちは、「ネンボちゃん」とよんでいた。)を追うのである。泳いでいた子が、急きょ、フンドシでさかなを追うというユーモラスな光景もしばしば見られた。
カニも大きいのがたくさん取れた。凧(たこ)糸で編んだ自家製の網の中に、魚の頭などを入れて沈めておくと、力二が入ってきて、おもしろいくらい簡単に取れた。取ったカニは、湯がいて食べると、甘みがあって、とてもおいしかった。子供たちにとっては、おやつであったが、大人たちは、これをさかなに酒を飲む人が多く、子供が力二を取って帰ると、父親が最も喜ぶという家が多かった。
ウ 故郷の山や川のこと
大洲、あるいは肱川というと、やはり、朝霧が思い出される。
最近は、朝霧がかかることが少なくなったが(*2)、昔は、よく朝霧がかかり、しかも、晴れるのが、今よりもずっと遅かった。霧の季節は、主として秋から冬にかけてであるが、夏でもよく霧が出ていたので、夏休みには、涼しさを求めて、親類などがよく遊びに来た。
**さんは、結婚後、仙台で生活をされたが、仙台は、いつも早くから日が当たるので、最初のころは、朝早くから飛び起きて御主人によく笑われたそうである。時計が止まっているのではないかと思ったことも少なくなかったと、当時を懐かしむ。
**さんも**さんも、戦争で焼け出されて大洲に帰ってこられたが、戦後は、子育てや生活に追われ、食べさせるのと着せるのが精一杯の毎日で、子供を川で遊ばせたり、ゆっくりと自然を眺める余裕はほとんどなかった。子供も独立し、ある日ふと肱川の堤防に立ったとき、大洲はこんなに山が近かったかと、あらためで感じたそうである。
最近は、子供たちが川で泳ぐこともほとんどなくなり、肱川が人々の生活から離れてしまったと、**さんはよく感じる。昔は、子供たちが、唇を紫色にしながら、一日中、川で遊んでおり、肱川のいたるところに、子供たちの歓声が満ちあふれていた。大人たちも、昼は網を持って川に行き、夜はカンテラ(手さげの明かり)をともしてアユを追うというように、みんなが川とともに暮らしていた。時間そのものが、肱川の流れのようにゆったりと流れ、人々の生活にも落ち着きがあった。時の流れとともにわたしたちを取り巻く環境が変化する以上、川と人とのかかわりが変化するのはやむをえないことなのかもしれないが、いつまでも変わらずにいてほしいものも多い。大洲盆地の生活文化の底流をなす肱川と人々とのかかわりもそうあってほしいものの一つではないだろうかと、**さんは考えている。
**さんは、御主人をなくされて独り住まいであるが、今は朝霧会という短歌の会に入り、肱川を題材とした歌を作られている。
霧深き 大洲の里の 暁け遅く 独り住居の 老い冬ごもり
**さんは、「一生を大洲で、と思っている。」そうである。大洲に生まれて、大洲に住んでいる以上、良くても悪くても、肱川から離れられない、というのが、大洲で育った人々の共通の思いではないだろうか。
*2:この原因としては、鹿野川ダム建設後の肱川の水量・水温・さらには大洲盆地の都市化の進展や土地利用の変化等が関係
しているものと推定される。(横山昭市編著『川の文化誌 肱川人と暮らし』 P38 愛媛県文化振興財団』)
|
写真1-1-2 肱川河原(城山対岸の肱川緑地公園)
平成6年11月撮影 |

 えひめの記憶 キーワード検索
えひめの記憶 キーワード検索